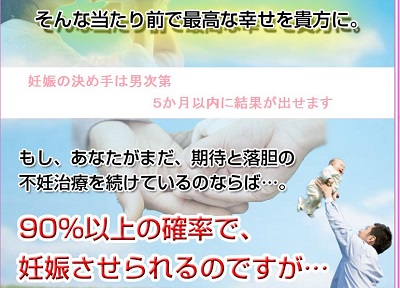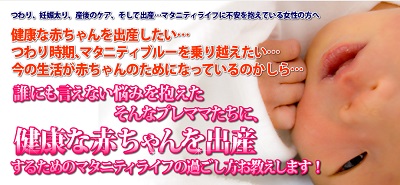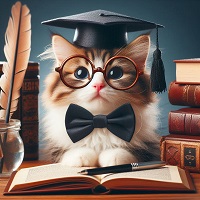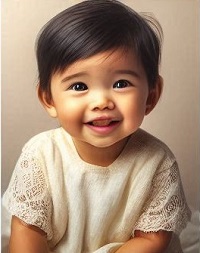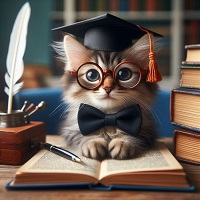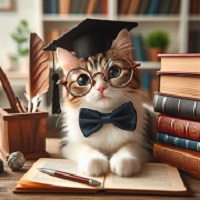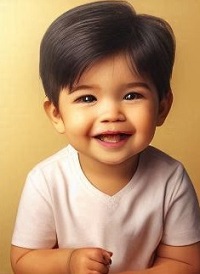まずは、子宮内膜の働きについて!
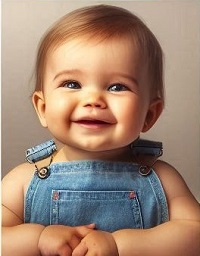
子宮内膜とは、子宮の内側にある粘液組織のことで、受精卵が着床して成長するために必要な赤ちゃんの大事なベッドです。そして、受精卵が着床しなかった場合は、不要となった子宮内膜は月経として体外に排出されます。
子宮内膜症というのは、子宮内膜が排出されるときに、他の器官に内膜が移動してしまって、その場所でも周期に合わせて子宮内膜が増殖してしまう状態です。
子宮以外に子宮内膜があるとダメなの?
残念ながら、あまり良い状況とは言えません。
子宮内膜組織は、女性ホルモンの働きで定期的に増殖・はく離(月経)を起こす働きがあります。子宮以外に移動した子宮内膜も、この女性ホルモンの影響を受けて増殖・はく離が起こるのです。
子宮内膜の増殖・はく離が子宮内で起これば、月経として体外に排出されるのですが、子宮以外の器官だと月経として排出できません。そのため、その場所でどんどん溜まって、炎症や癒着などを引き起こします。
子宮内膜症の原因について

子宮内膜症の原因については、決定的なことは分かっていません。月経血の一部が逆流して子宮以外に移動したり、子宮内膜ではない細胞が、子宮内膜に似た組織に変わって増殖・はく離を起こすと言われています。
また、子宮内膜症になっても、絶対に妊娠できないわけではありません。ただ、子宮内膜症を放置して症状が悪化したり、子宮内膜症が発生した場所によっては、不妊の原因となる場合があります。
子宮内膜症の検査と治療
子宮内膜症の検査には、超音波や血液検査・CTなどがあります。また、子宮内膜症の治療は、ホルモン療法や手術で病巣を取る方法があります。ただ、子宮内膜症は、とても再発しやすい病気ですので注意が必要です。
● 薬による治療
子宮内膜症は、月経のたびに悪化する危険性があります。そのため、薬で生理を止めて、その間に炎症を鎮めたり、溜まっている血液などを体に吸収させます。このような薬物療法には、擬妊娠療法や擬閉経療法などがあります。
● 手術による治療
手術療法では、患部を直接見て正確に治療ができます。ただ、入院が必要だったり、術創が出来る難点があります。開腹せずに腹腔鏡で手術を行う場合には、入院期間も短く、傷跡もあまり目立たないのですが、症状が悪化している場合には、腹腔鏡手術では治療ができないこともあります。
不妊症となる子宮内膜症 (チョコレート嚢腫)
卵巣内部に子宮内膜症ができて、古い血液が溜まっている状態を「チョコレート嚢腫」と言います。この卵巣にある子宮内膜組織も、増殖・はく離を繰り返しますので、古い血液が溜まって卵巣が腫れてきます。
また、チョコレート嚢腫が悪化すると、卵巣髄質内にまで広がることもあり、卵巣のほぼ全体を占めるほど大きくなる場合があります。このチョコレート嚢腫の治療には、腹腔鏡手術や開腹手術、薬物治療などあります。